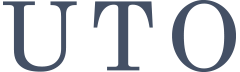羊绒“消亡”的故事
缓慢而仔细地染色的深沉而优雅的颜色。舒适且安全的颜色。

羊绒和颜色
色彩是时尚中非常重要的元素,俗话说“色彩第一,图案第二,结构第三”。
事实上,时尚离不开色彩,而色彩对于毛衣来说尤其重要。
这次我们就来说说“染色”它的“死”。
染色工匠们夜以继日地努力研究如何将织物染成最好的颜色。
根据颜色挑选绒山羊

美丽的色彩
一级原羊绒
羊绒原毛根据“线的细度、纤维长度、杂质含量”分为9个等级,但UTO使用的是东洋纺织的“1级原毛”纺成的羊绒纱线。
“一级原羊绒羊毛”具有极高的白度(白度),高白度的线的特点是染色时颜色鲜艳度和深度增加。
另外,绒山羊之间也存在个体差异,羊绒颜色有白色、灰色、棕色等。有时这些头发会被原样使用,但大多数时候它们会被染成某种颜色。
①白色

②灰色

③棕色

如果颜色像羊毛一样容易脱落,那还好,但羊绒羊毛非常娇嫩,如果去掉颜色再染色,就会受损,失去质感。
因此,例如,亮度低的颜色可以用“棕色”或“灰色”的头发来染,但白色、萨克斯、和等较浅的颜色只能用“白羊绒”的头发来染。粉色的。
顺便说一句,UTO有许多明亮清晰的颜色,因此经常使用“白羊绒”。

罕见的明亮羊绒颜色
战后开始销售羊绒制品时,颜色都是驼色、灰色、酒红色、海军蓝、黑色等低亮度颜色。
当时,这些颜色被称为羊绒颜色,据说是“羊绒特有的大胆而深沉的颜色”。但实际上,在外汇稀缺的日本可以买到的线,有棕色羊绒或灰色羊绒,还有昂贵的白色羊绒等。现实似乎是被西方买走了,从未流通过。
因此,当人们看到UTO鲜艳多样的颜色时,常常会感到惊讶,说:“羊绒可以有这么漂亮的颜色。”
考虑纹理和深色

顶染
纤维染色有毛条染色、丝线染色、成品染色三种。
纤维(不仅仅是羊绒)可以在其原始状态(毛条染色)、纱线中(纱线染色)或制成产品后(产品染色)进行染色。每种染色方法根据用途不同而不同。
UTO的羊绒纱线采用“上条染色”染色。
与“线染”和“产品染色”线相比,“面染”线具有更好的保色性和更深的色调。
完成颜色需要时间和精力,增加了成本和风险,但我们讲究“顶染”,以便订购的人可以长时间享受颜色。
另外,“顶染”是一种对自然温和的染色方法。
UTO之所以讲究“毛条染色”,是因为它有助于减少用水量、减少废水和污染,这意味着保持自然环境的清洁。

重视高风险“顶染”的质感
对于无法重新染色的线,染色越早,风险就越高。如果用顶染将棉布染成红色,线就会是红色的,当然产品也会是红色的。
一步染色后的纱线染色比毛条染色的风险要小得多。
你越能吸引并染上随流行趋势而快速变化的颜色,风险就越小。如果可能的话,你可以在淡季用未漂白的材料制作一件毛衣,一旦了解了流行的颜色流行趋势,就可以染色。淡季,所以你可以抓住一个很好的机会。你可以的。
意大利制造商贝纳通 (Benetton) 完善了这种梦幻般的产品染色工艺。这是贝纳通伟大突破的开始。我认为这是革命性的。
但对于细腻的羊绒来说,不可能采用如此大胆的方法,否则会破坏质感。

日本先进技术“低温染色”
染色的基本方法是在含有染料的热水中浸泡。虽然根据颜色的不同而有所不同,但染料渗透到纤维中需要一定的温度和时间。
保色度也称为“牢度”。
一般来说,当试图“提高牢度”时,有必要“提高染色温度”。
较高的染色温度具有“染色更快、更均匀”的优点,但另一方面,较高的温度会损坏羊绒纤维并降低其质地。
此外,这可能会导致纱线难以编织并出现破洞。

牢度和质感是矛盾的,因为“提高牢度”使“颜色不褪色”和“降低质感”是矛盾的,但向UTO提供纱线的东洋纺工业公司,为了满足针对这些要求,我们开发了一种特殊的方法,称为“低温染色”。

“低温染色”保持柔软质感
UTO的羊绒纱线采用东洋纺织专有的“低温染色”技术进行染色,以尽可能保留羊绒的蓬松手感,使其成为保色性好的纱线。
“在低温下缓慢染色,以确保颜色均匀。”
这是基于多年经验的先进染色技术,在世界各地广受好评。
虽然需要仔细控制时间和颜色,但这种独特的染色技术保留了羊绒纤维的光滑质感,在保色性和质感方面保持了高品质。

这样一来,UTO的品质得到了染色大师的支持,但实际上,即使采用最好的技术,根据颜色的不同,质感也存在细微的差异。
当然,即使是黑色等深色,羊绒也比其他材质柔软无比,但也不可避免地比其他柔和颜色的线硬。即使是相同型号的毛衣,根据颜色的不同,也会有不同的质感。
色彩工匠们每天都在不断努力,创造出更好的色彩和更好的质感,但仍然存在难以克服的技术障碍。 。
但无论如何,黑色羊绒总是很受欢迎(笑)
通过混合颜色创建的“深色调”
羊绒棉采用最高等级的羊绒羊毛,经过纱线染色和低温染色制成,在保持质感的同时带出最大的活力和深度。
UTO的羊绒纱线是由5到10种颜色的羊绒棉“混纺”成单一颜色。

例如, UTO的颜色“皇家蓝”是由五种蓝色混合而成。
另外,在“中灰色”的情况下,混合了黑色、白色、浅米色、浅紫色和蓝色。
蓝色很难被注意到,但它就像一种增加颜色深度的秘密成分。
通过混合颜色,您可以增加颜色的深度,甚至使浅色粉彩看起来更加浓郁。

混合还“显着稳定了颜色变化”。
当涉及到颜色时,例如当您想要重复相同的颜色时,颜色稳定性会带来安全感。
UTO始终使用相同的羊绒线和颜色,因此为了让您对UTO的羊绒针织品感到安全,“颜色稳定性”是一个非常重要的因素。